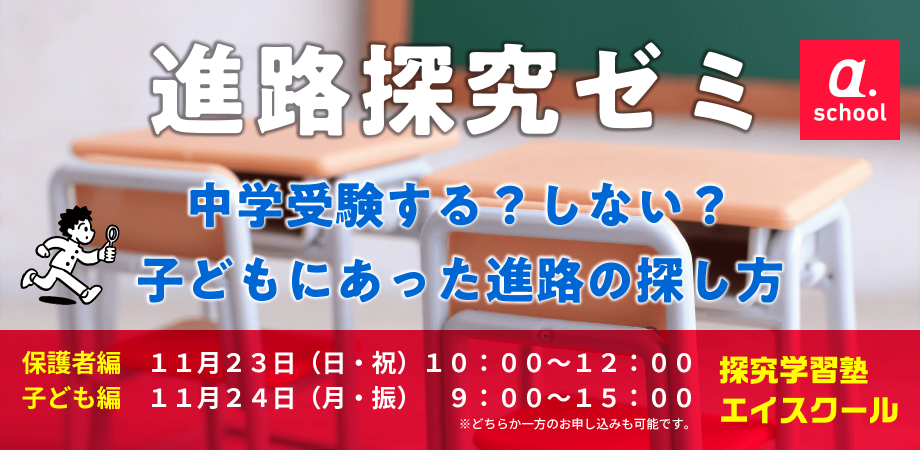「探究型中学入試」の最前線って?
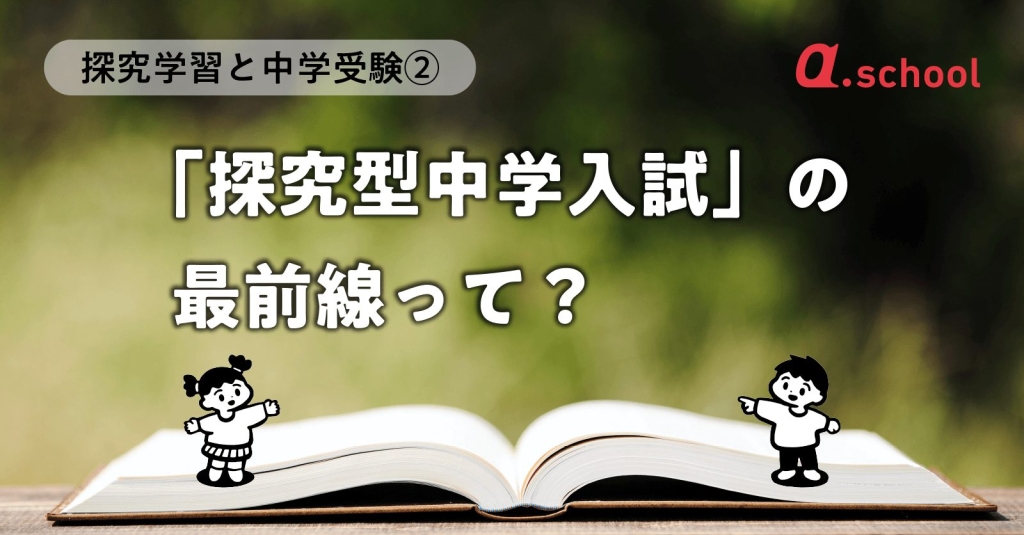
ここ20年で中学入試の風景は大きく変わりました。従来の4科目(国算理社)一択から、算国のみの2科目入試、思考力・表現力を問う適性検査型へと多様化が進み、すでに「メジャーな選択肢」として定着しています。
その延長線上で、じわりと存在感を増しているのが「新型」「探究型」と呼ばれる入試です。まだ実施校は多くありませんが、知識の量や活用力だけでなく、受験生の探究心、問いを立てる力、思考の深さ、表現力、創造性そのものを見極めようとしている点に、この新しい入試の核心があります。
この潮流を一言でいえば、「探究型授業の入試化」です。探究・PBL(Project Based Learning)に力を入れている学校が、入学後の実際の授業に近い体験を入試の場に持ち込む。受験当日だけの出来栄えではなく、事前の準備やふりかえり、さらには他者との協働までを含めて評価する。つまり、「この子がこの学校の学びを主体的に楽しめるか」「この学校で学び続けたときに伸びるか」を、よりリアルな学びのプロセスから読み取ろうとする試みだといえます。
探究型の入試は学校ごとに設計思想が異なりますが、実際の入試問題の特徴をもとにあえて分類して整理してみました。
探究型中学入試の6タイプ

①自己PR型
小学生生活の中で自分が打ち込んできたことについて、口頭でプレゼンテーションを行い、面接官との質疑応答でさらに深掘りする形式です。評価の中心は、「なぜそれに取り組んだのか」という動機、「自分の強みや魅力はどこにあるのか」という自己理解、「何に徹底的にこだわり、どのように壁を乗り越えたのか」という過程、「得られた学びを次にどう活かすか」という展望などです。
単なる成果物の出来栄えではなく、そこに込められた想いや意図、思考・発見がどれだけ言語化されているかが鍵となります。面接では、質問の意図を的確に汲み取り、説明の順序や焦点を切り替える柔軟さも見られます。
【具体的な入試内容のイメージ】
「これまであなたが最も力を入れてきた活動を7分間でプレゼンテーションしてください。活動の内容や結果に加え、その意義と今後の発展可能性にも触れてください。」
「自分の作品(研究ノート・ロボット・絵画・楽曲など)を持参のうえ、10分間で紹介してください。その中で、特にこだわった点、制作過程で直面した課題、その解決のために試した方法についても説明してください。」
出題校:国士舘中学校、関東学院六浦中学校、東京立正中学校 ほか
②テーマ探究型
学校から与えられるテーマについて探究する形式です。事前に調査や準備を行い、受験当日にはスライドやポスター、紙芝居などの資料を用いて発表する「プレゼン型」や、入試当日にさまざまな資料や情報が提示され、それをもとに自分なりの考察や探究のアプローチをまとめて表現する「論述型」などがあります。テーマとしては、社会的な課題や時事トピックが取り上げられる傾向が強いのが特徴です。
重要なのは、そのテーマを表面的にまとめるのではなく、背景や構造をしっかりと理解したうえで、誰かの意見の受け売りではなく、自分自身の視点からオリジナルな考えを導き出せているかどうかです。また、自論の論理的な構成(主張―根拠―具体例―反論への応答)、使用する情報の信頼性、そして発表資料のわかりやすさや表現力なども、評価の重要なポイントとなります。
【具体的な入試内容のイメージ】
「もしあなたが日本のリーダーなら、世界平和のためにどんな政策を優先しますか。根拠となる事実やデータを示しながら提案してください。」
「あなたが『子ども食堂』を運営するなら、持続的に食事を提供するためにどんな仕組みを整えますか。運営上の課題と解決策を示してください。」
「指定の書籍を読んだうえで、自分が興味を持ったこと・もっと深く知りたいと思ったことを選び、探究するための問いを立ててください。また、それを明らかにすることが、あなた自身や社会にとってどんな価値をもつのかを説明してください。」
実施例:日大豊山女子中学校、かえつ有明中学校 ほか
③デザイン・ものづくり型
身近な対象を観察したり、自分の日常生活を振り返ったりしながら、自分なりに課題を見つけ、その課題を解決するためのアイデアを考え、実際に形にして検証することに挑戦する形式です。作品を提示するだけでなく、そこに至る過程や気づき、完成した作品の意味などを文章で説明し、一連の探究プロセス全体が評価されます。試験時間中にレゴや工作素材などが与えられ、手を動かしながら作品をつくる体験型の出題が行われるのも、この形式ならではのユニークさです。
評価されるのは、成果物そのものの完成度だけではありません。課題を自ら発見する力、アイデアや作品に現れる独自の視点や切り口、作りながら考えを更新していく試行錯誤の姿勢、そして過程や背景を言語化して伝える力などが総合的に見られます。
【具体的な入試内容のイメージ】
「『自分の性格』『自分が嫌だと思う状況とその時の感情』『その状況を解決するアイデア』をLEGOで表現し、それぞれの作品について文章で説明してください。」
「7本の鉛筆を書き比べたり観察したりしながら、気づいたことを書き出して整理してください。また、なぜ鉛筆にはさまざまな種類があるのかを考察してください。そのうえで、7本の中から不要だと思う1本を選び、その理由を説明するとともに、その課題を解決する新しい鉛筆のアイデアを描いて説明してください。」
実施例:聖学院中学校 ほか
④プログラミング型
提示されたミッションに対して、Scratchなどのビジュアルプログラミング言語や教育用ロボットを用いて実装し、その動作を実演・説明する形式です。③のものづくり・デザイン型と入試の構造は似ていますが、アナログなアプローチにとどまらず、パソコンやタブレットを使って実際にプログラムを組み込むデジタルな探究が主軸になっている点が特徴です。
評価されるのは、完成した成果物そのものだけではありません。プログラムの構造や工夫の意図、デバッグや改良を重ねる中での試行錯誤の過程なども重視されます。高度な技術力を競う試験ではなく、プログラミングを手段として課題をどう理解し、どのように解決へと導いていくか――課題解決の姿勢と考える力が問われます。
【具体的な入試内容のイメージ】
「センサーを活用して、さまざまな色や形のブロックを仕分けるプログラムを作成してください。誤判定が起きないように、プログラム内でどのように工夫したかを説明してください。」
「スタートからゴールまで障害物を避けて走行するロボットを実装し、プログラム設計で工夫した点とその意図について説明してください。」
実施例:追手門学院大手前中学校、武庫川女子中学校 など
⑤ワークショップ型
当日集まった受験生同士でチームを組み、短時間で課題解決やアイデア創出に取り組み、最後に共同で発表する形式です。個人の知識量や発表力だけでなく、役割分担、合意形成、時間管理、相互フィードバックといった協働の基礎力が評価されます。入試で扱われるテーマやミッションは②〜④の形式と共通するものが多いですが、個人ではなくグループで挑む協働型の探究であることが最大の特徴です。
【具体的な入試内容のイメージ】
「AIとともにつくる理想の未来とは、具体的にどのような姿でしょうか。また、AIが社会に悪い影響を及ぼしてしまった未来とは、どのような姿でしょうか。グループで議論したうえで、今後のAIとの付き合い方について提案してください。」
「バリアフリーやユニバーサルデザインという概念を理解したうえで、身近な環境(学校)を観察し、課題を見つけ、改善のためのアイデアを提案してください。」
実施例:和洋九段女子中学校、かえつ有明中学校、関西創価中学 ほか
⑥グローバル型
英語でのスピーチやプレゼンテーション、ディスカッション、質疑応答を通して、内容の論理性と言語運用を総合的に確かめる形式です。単に英語が話せるかではなく、相手の問いを理解し、自分の主張を再構成して伝える対話力が重視されます。資料を英語で読み取り、要点を整理してわかりやすく再構成できるかも大切なポイントです。②の探究テーマ型や⑤のワークショップ型の要素を取り入れ、英語を使って社会的な課題や身近なテーマについて考察・協働・発表するケースも見られます。
【具体的な入試内容のイメージ】
「”Should homework be mandatory for junior high students?”(中学生には宿題を必ず出すべきだと思いますか?)という問いに対して、賛成または反対の立場を明確にし、その理由(根拠)と、予想される反論に対する自分の考えをまとめて発表してください。」
実施例:日大豊山女子中学 ほか
探究型入試の共通点──体験を通したマッチング
探究型入試に共通するのは、入学後の学び方と強く接続した「入試体験」をつくっていることです。SDGsや時事トピックなど、正解のないテーマが提示され、一般的な筆記形式ではなく、プレゼンテーションや作品づくり、協働ワーク、ふりかえりなど、入試の中にリアルな学習プロセスが組み込まれています。
形式も当日一発勝負に限らず、事前に課題が発表されて準備期間を設けるものや、日々の取り組みや探究活動そのものを評価対象とするものなど、さまざまな形で実施されています。
さらに注目したいのは、評価観点の明文化です。多くの学校が、自校の教育方針を反映した評価軸(ルーブリック)を用い、結果だけでなくプロセスを公正に評価しようとしています。これにより、「その子がこの学校の学びでどのように伸びていけるか」という適合性を多面的に判断する仕組みが整いつつあります。
実際に何が問われているのか──あくまで「日常の探究」の積み重ねの延長に入試がある
このような探究型入試で本当に問われていることは何か。
単なる知識やスキルの有無ではありません。一言でいえば、「日々の暮らしの中で、どれだけ自分なりに探究し、表現しているか」ということだと思います。
何に心を動かされ、どんなモチベーションや原動力で行動しているのか。その子なりのものの見方やアプローチに独自性はあるか。正解のない課題に対して、自分なりに粘り強く向き合う姿勢があるか。そうした探究の営みが日常の習慣として根づいているか。ーーそういった点が見られています。
そして、その積み重ねを通じて、探究を支える地力――問いを立てる力、考えを深める思考力、自分の言葉で表現する力、相手に伝える力、そして活動を振り返り次につなげる力ーーが、日々の学びや生活の中で自然と育っているかどうかが問われます。探究型入試は、まさにその「学びの根っこ」を見極めようとする入試なのです。
「探究」「創造」の芽を育てる学び舎ーー探究学習塾エイスクールの役割
そうした力は、まずは日常のご家庭や学校の中で少しずつ育まれていくものだと思います。
一方で、世の中にあるさまざまな探究テーマの面白さに触れて視野を広げたり、子どもの特性に合わせて時間をかけながら探究活動に伴走したりすることは、ご家庭や学校だけではなかなか難しいこともあります。
だからこそ、第三の学び舎をうまく活用することで、子どもの探究や創造の学びをぐっと広げ、より深めていくことができます。私たちエイスクールのことも、ぜひ気軽に頼ったり、活用してもらえたらうれしいです。
またエイスクールでは親子で「中学受験」「進路」を探究する講座「進路探究ゼミ」を年2回開催しています。
進学塾ではないエイスクールだからこそお伝えできる、必ずしも中学受験を前提としない進路探究の講座です。
《保護者編》《子ども編》の二部制で開講することで、それぞれの立場における進路との向き合い方に加え、親子で協調して進路を模索するコツなどをお届けします。
次回は2025年11月23日、24日に開催します。1日からの参加も可能です。ご興味ある方はぜひこちらのイベント特設ページをご覧ください。